「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」
これは、アドラー心理学で有名なアルフレッド・アドラーの言葉です。
家族、友人、恋人、同僚・・・
私たちを取り巻く人々は人生に喜びをもたらしてくれますが、ときに振り回され、ストレスの原因にもなります。
今回は『嫌いな同僚』をテーマに、
『どう付き合っていけばいいの?』
『もしかして私も嫌われてる・・・?』
と悩んでいる方が、職場の人間関係で心を消耗しないためにできることを考えていきたいと思います。
職場の同僚がストレス!!・・・そもそもストレスってなに?
「ストレスってなに?」という説明は不要ですよね。
とくに社会人にとっては日常的なもので、「〇〇がストレスで」と口にすることはあっても、その対象について「なぜストレスを感じるのか」ということまで深く考える余裕はほとんどありません。
ストレスとは「外部から刺激を受けたときに生じる緊張状態のこと」です。
もっと分かりやすく言うと、「脅威」を感じたときに抱く不安・危機感・恐怖心といった心の動きがストレスの正体です。
私たちは「自分が大事にしているもの・価値観が脅かされる」と感じたときに脅威を覚え、本能的にそれを遠ざけようとします。
つまり「職場の人間関係がストレス」という人は、職場の人間関係に対して「自分の大事なもの・価値観が脅かされる」と脅威を感じ、距離を置きたがっている状態と言えます。
大事にしているもの・価値観というのは、例えば職場における自分の評価であったり、ポジションであったり、他人に嫌われたくないという感情だったりします。
また、「ストレスに強い人・弱い人」という言い方をしますが、大事にしている価値観や物事の捉え方は人それぞれなので、ストレスを感じる対象や程度に個人差があるのは当然のことです。
ある事象について、すべての人が同じようにストレスを感じるとは限りません。
「Aさんが嫌いでストレスを感じる私」と「Aさんとは気が合うし、仕事がやりやすいと感じているBさん」がいるのは、価値観や物事の捉え方が違うためであって、「私だけAさんとうまく付き合えない」と塞ぎ込む必要はありません。
誰にでも「嫌いな人」はいる

職場に嫌いな同僚がいるあなたは、「嫌いな同僚とどう付き合っていけばいいのか?」ということに大きなストレスを感じていることでしょう。
じつは、「嫌いな同僚」というストレスの対処法は思っているよりもシンプルで、結論からお伝えすると、自分の中の「嫌い」という感情を抑え込まず堂々と認めることです。
人間関係の悩みは「相手がどんな人間か」ということよりも
「その人を嫌悪する自分」にストレスを感じているため、「人を嫌うのは自然なことで悪ではない」と容認することが人間関係をストレスフリーにするためのコツです。
小さい頃に刷り込まれた「みんなと仲良くしましょう」という常識は、「良好な人間関係を築けないのは悪」という空気となり、やがて「嫌いな人がいてもなんとか上手くやっていかなければならない」「他人に嫌われてはいけない」という歪んだ思考になります。
しかし、食べ物やファッションに好き嫌いがあるように、人に対しても好き嫌いがあるのは当然のことです。
「嫌いな人」がいてもいいのです。むしろそれは、ごく自然な感情であって悪いことではありません。
まずは「人を嫌うのは自然な感情だ」と認めることからはじめてみましょう。みんなが仲良しである必要はないのです。
「嫌いな人は嫌いだし、合わない人は合わない」と割り切って考えたほうが、ずっと楽に生きられるはずです。
なぜあの人が苦手なのか?人を嫌う理由とメカニズム
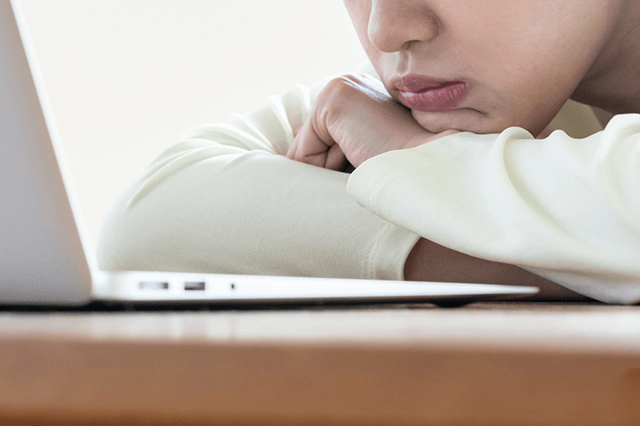
中島義道著「ひとを“嫌う”ということ」(角川文庫)の中で、人を嫌う理由が次のように挙げられています。
◉人を嫌う理由
1. 相手が自分の期待に応えてくれない
2. 相手が自分に損失を与える可能性がある
3. 相手に対する嫉妬
4. 相手に対する軽蔑
5. 相手が自分を「軽蔑している」と感じる
6. 相手が自分を「嫌っている」と感じる
7. 相手に対する絶対的無関心
8. 相手に対する生理的・観念的な拒絶反応
これらを見ると「嫌い」という感情に至るには、相手への「期待」や「憶測」といった主観的で根拠のない理由が多いことに気付きます。
とくに5.や6.の理由は、直接相手から聞き出したわけでもなく、かなり客観性に欠けた(被害妄想的な)感情だと思いませんか?
人を嫌う理由は、心理学でいう「投影」が大きく影響しています。投影とは精神的な防衛規制のひとつで、認めがたい自己の衝動や事実を都合のいいようにねじ曲げて、他人にその悪い面を押し付けてしまうような心の動きをいいます。
つまり人を嫌う理由の多くは自分の中にあって、「あの人は〇〇だから嫌い」というのは自分を正当化するために後付けした理由であることが多いのです。
「人を嫌いになる」というのはごく自然な感情だとお話ししました。
「なぜ嫌いなのか」と問われたら「嫌いなものは嫌いだから」という答えが正解なのですが、多くの人がそれをよしとせず、自分の「嫌い」という感情を正当化しようという心理が働くわけです。
「自分が悪いのではなく、あの人が〇〇だから嫌いなのだ」と理由付けすることで、心の平穏を保っている。「人を嫌うメカニズム」には、こんな複雑な側面があるのです。
嫌いな同僚を無理に好きになる必要はない

多くの人が「嫌い」という感情を適切に処理できず自己嫌悪に陥り、それによってストレスを感じるということは、「嫌い」という感情を受け入れることができれば人間関係の悩みはほとんど解決できるのではないでしょうか。
無理に好きになろう・関係を修復しようとすると自分の感情を抑圧し、自分で自分を振り回すことになるためおすすめできません。
「人を嫌う・人に嫌われるのは自然な感情」という前提を忘れないことが、人間関係を築くうえでのいちばんの秘訣と言えるかもしれません。
嫌いな感情と仕事は切り離して考える
「嫌い」という気持ちを抑え込まず、当たり前の感情として認める。
言葉でいうと簡単ですが、この境地に達するまでにはそれなりの時間と訓練が必要です。
職場の嫌いな同僚を眼の前にしたとき、あなたはどんな心境・態度になるでしょうか?
私の経験を例にお話しすると、嫌いな同僚がいると考えただけで憂鬱になる・目の前にいると緊張してオドオドした態度になる・萎縮してしまい言うべきことが言えないなど、存在そのものが苦痛で仕方ありませんでした。
業務上必要なことをきちんと伝えられないことで相手をイライラさせるだけでなく、結果的にほかの同僚やお客様に迷惑をかけてしまったこともあります。
しかし、報告や相談がまともにできず、それが原因で仕事に支障が出るというのは避けなければいけません。職場においては、「嫌い」という感情は認めつつ仕事と切り離して考えることが必要なのです。
例えば、挨拶をする・お礼を言う・報告や相談をするといった基本的なことは嫌いな同僚に対してもきちんとすべきですし、「嫌い」という感情をあらわにして職場の雰囲気を乱すようなことは避けるべきです。
それでもうまく付き合えない場合は
嫌いという感情を認めつつ、仕事とは切り離して考える。
この切り替えがうまくいけば職場に嫌いな同僚がいてもあまり問題はないはずです。
しかし、気持ちを切り替えられない・苦痛で仕方ない・職場を離れても嫌いな同僚のことを考えてしまう・・・というときは、配置換えなどを上司に相談しましょう。
人間関係の悩みにおいて、「嫌う」と同様「逃げる」というのも悪いことではありません。「どうしても無理!」と思ったら、その場からさっさと逃げるということも対処法のひとつとして覚えておきましょう。
まとめ

多くの時間をともにする職場の人間関係は、仕事だけでなく健康や生活の質をも左右する存在です。退職・転職の理由の多くが「職場の人間関係」であることからも、あらゆる職場で人間関係を築くことがいかに難しいか容易に想像できます。
今回は「嫌いな同僚」をテーマに、「人を嫌う」という感情やその対処法についてお話ししました。「人を嫌う」という一見するとネガティブな感情も、見方を変えてうまく付き合うことで問題解決の糸口がつかめるはずです。
この記事が、読んでくださったあなたの人間関係のヒントになることを願っています。
プロフィール
遠藤 愛
ライター、看護師。
女だらけの職場に長年勤務。大人の女性のために、自身の体験をもとにしたリアルな記事をお届けします。










